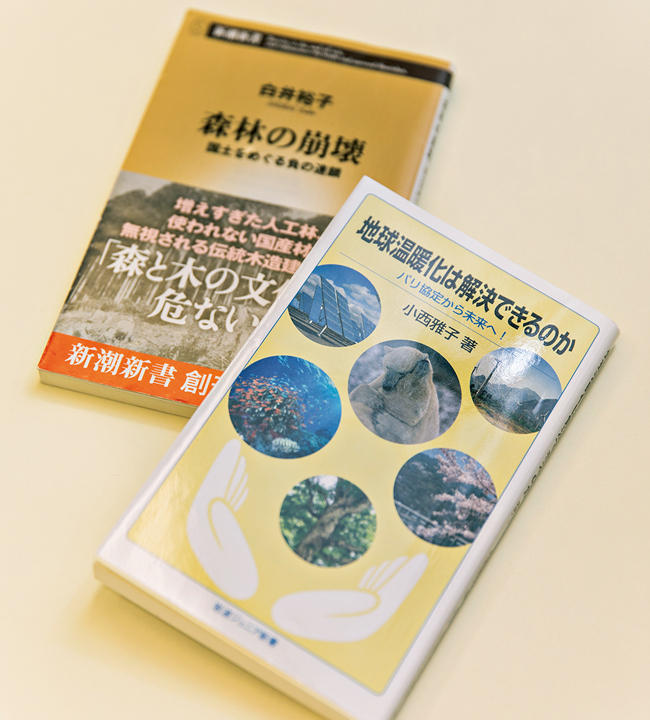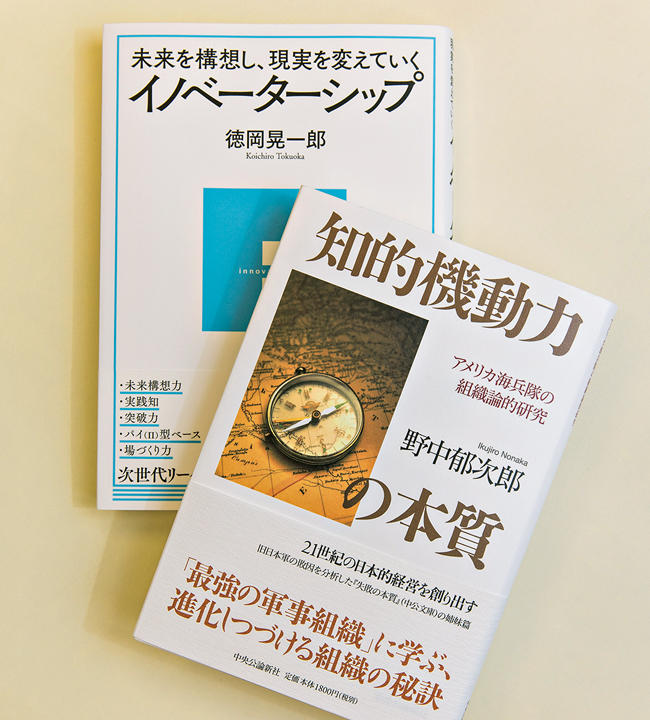書店は世相の映し鏡。行けば「今」がよくわかる
さて、今度は斎藤氏の読書習慣に注目したい。
仕事柄、週末もサーキットやディーラーへ出向くために、近頃はもっぱら手軽に持ち運べるkindleで本に親しんでいる斎藤氏だが、その反面で、書店に足を運ぶ意義を改めて実感しているという。その理由を訊ねてみると、彼はきっぱりした口調で言った。
「書店には世相が反映されています。それを皮膚感覚で味わえるのがアナログの良さですね」
そして、ちょっと考える素振りをして、再び言葉を継いだ。
「デジタル化が進むと便利になりますが、だからといって楽になるわけではない。むしろ不確実性が高まります。だから、生きる指針を与えてくれるものを人は余計に渇望するのではないでしょうか」
そう言って、一冊の本を取り出した。タイトルは『知的機動力の本質』。サブタイトルに『アメリカ海兵隊の組織論的研究』とある。
「軍隊にとっては技術的訓練が第一で、それが唯一かと思っていましたが、この本を読んだら、インテリジェンスを追求することの方が大事であり、それこそが近代の海兵隊の組織文化であるとわかって感心しました。戦略コミュニケーション・コンサルタント会社のフライシュマン・ヒラード・ジャパンで社長を務める徳岡晃一郎氏が著した『未来を構想し、現実を変えていく イノベーターシップ』にも近いことが書いてありましたね。今や情報を取捨選択するだけで時間がかかり、腰を据えて物事を考えづらくなっていますが、だからこそ、意識して内省力を鍛えていくべきではないでしょうか」
確かに、便利さは弊害ももたらす。それを自覚し、弊害をなくすように対処することが大切だ。
「我々が扱うクルマも人生を豊かにする便利な道具であると同時に、環境を破壊したり、人に危害を加えたりと負の側面も持っています。そのマイナスの部分をクリアにしていくのが自動車会社の使命。自動運転に取り組んだり、電気自動車の開発に努めたりして。私は山登りの趣味を持っていることもあって、環境に対する負担を軽減することに、もとから強い関心を寄せていますが、我々がこれを本気でやらなければ、いつか自動車産業は滅びてしまう。環境に関する本はいい戒めになりますね」
BOOK
環境対応は経営における永遠の課題。
特に今日は内省力を磨くことも必要。
GLASS
単なる美しさは求めない。
目的の伴った機能美に心惹かれる。

顔の印象を邪魔しないシンプルなフォルム
リムの細さに加えて天地も狭く、主張しすぎないデザインなのでオフィシャルな場面に最適。また、斎藤氏は頭痛持ちで、メガネに締め付けられるのが好きではないとのことだが、「軽くてフィット感がいいのでストレスを感じない」(斎藤氏)と納得している様子だ。

デザインと技術を調和させたアイウェア
斎藤さんが仕事をする際に用いているメガネはアラン ミクリ。レンズの外周をリムで完全に覆うことによって強度を高める一方、テンプルのカラーと柄でウィットを効かせている。
[MEN’S EX 2018年10月号の記事を再構成](スタッフクレジットは本誌に記載)